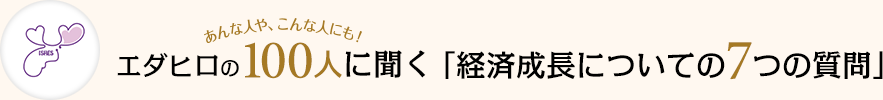100人それぞれの「答え」

088
キューバ研究家
吉田 太郎(よしだ たろう)さん
いま、ラテンアメリカでは、アンデスやアマゾンの先住民の世界観をベースに「ブエン・ヴィヴィル(良く生きる)」という考え方が、成長へのオルタナティブとして登場し、エクアドル憲法(2008年)やボリビア憲法(2009年)にも位置づけられています。
- Q. 経済成長とはどういうことですか、何が成長することですか
-
多くの方が指摘しているように、現在GDPで測定される経済成長とは数値のやりとりです。現実の財やサービスのやり取りが成長していなくても、ペーパーマネーや金融機関内を移動する電子上の数字が増えるだけでも経済は成長します。
そこで、経済を三つにわけて考えると経済成長が何かが明確化します。 「スモール・イズ・ビューティフル」で有名なE・E・シューマッハーは、自然からもたらされる財やサービスを「第一次財(primary goods)」、人間の労働からもたらされる財やサービスを「第二次財(secondary goods)」と呼び区別しました。
すべての経済活動のベースとなるのは、太陽エネルギー、石油や鉱物資源、水、土壌、生物多様性等、自然がもたらす「第一次経済」のサービスです。この「第一次経済」に人間の労働を加えることで、産みだされる農作物や工業製品等の「第二次経済」の財とサービスが生まれます。
ですが、米国のピーク・オイルの論客、ジョン・マイケル・グリアは著作『自然の富(John Michael Greer, The Wealth of Nature: Economics as if Survival Mattered, New Society Publishers,2011.)』で、自然からも人間の労働からも産み出されない「第三次経済」があると指摘します。金融商品の象徴されるマネー経済です。
さて、現在の経済学では「交換価値」として測定されないものは評価されず、その交換価値の尺度はマネーです。ですから、マネーの価値が付かない第一次経済のサービスは、経済的価値がないことになります。水も空気もタダなのはそのためです。
第二次経済の財やサービスは実体を持ちます。そして、需要が増えれば値段があがり、供給が増えれば値段が下がるネガティブなフィードバックが働きます。これが、アダム・スミスの言う「神の見えざる手」の秘密です。けれども、第二次経済は、第一次経済をベースとしていますから、需要と供給の法則が働くにも限度があります。例えば、石油の需要がいくら増えても、資源が限られていますから、それに応じて無限に供給量を増やすことはできません。
第三次経済のマネーも、第二次経済の実物経済の財やサービスとリンクしていれば、ネガティブなフィードバックが働きます。マネーで購入できる財やサービスよりも多くのマネーが流通していれば、インフレが起こりますし、流通しているマネーよりも財やサービスが多ければデフレが起こります。
けれども、第三次経済のマネーは、実物経済から解離して、マネーそのものを財として扱い、マネーをマネーと交換することが可能です。この場合、第三次経済に対する制約は人々の需要だけです。例えば、「金融商品」は実体がない人々の期待だけですから、需要が増えれば、それに応じて無限に供給量を増やせます。マネーは、人々が嬉々として買いたければ、紙と印刷インクさえあれば、いくらでも刷ることができるのです。ただし、こうした経済はバブルであって、必ずはじけることを過去の歴史は証明しています。
- Q. それは望ましいものですか、それはなぜですか
-
マネー経済の経済成長には問題がありますが、実物経済の経済成長は望ましいこともあります。上述した問題点を是正するため、ジョン・マイケル・グリアは、国内総生産(GDP)を第一次、第二次、第三次の経済に分類することを提唱しています。すると、総一次産品=GPP(gross primary product)は、油井から抽出される石油、鉱山から掘られる石炭等、経済化される未加工の天然産物の価値となります。
総二次生産=GSP(gross secondary product)は、自然の原材料や金融商品や金融サービスを除いた、すべての財・サービスの価値となります。
総三次生産=GTP(The gross tertiary product)は、すべての金融商品とサービスの価値、そして、その経済によって生産されたすべてのマネーとなります。こうすれば、GTPだけが急増していても、GPPやGSPが頭打ちとなって低下していれば、それは国が豊かになっていることを意味せず、第三次経済が膨張して投機的な破産で破綻する直前にあることがわかります。
一方、GSPが増えていても、GPPが増えていなければ、それは、ファクター4やファクター10のように、天然資源の利用効率を高めていることになります。こうした場合、その経済成長は良いことになりましょう。
- Q. それは必要なものですか、それはなぜですか。必要な場合、いつまで、どこまで、必要でしょうか、また経済成長を続けることは可能ですか、それはなぜですかね。
-
第二次経済も第一次経済に依存している以上は、無限に成長を続けることは不可能です。
意外に思えますが、自由主義を提唱したアダム・スミスも、国際分業論を提案したデヴィッド・リカードウも、経済成長論者ではありませんでした。彼らの主張は、明白で、食料も羊毛も農地をベースとしている以上、人口を増やすには食料生産が必要ですが、繊維産業を成長させるには食料生産を減らさざるを得ず、ゼロ・サムゲームにあると考えていたためです。
近代社会は科学技術の進歩によって誕生し、様々な問題もテクノロジーによって解決でき、成長を続けることが可能だいうのは現代の神話です。産業革命はワットの蒸気機関の発明がひとつの契機となりましたが、蒸気機関の理論そのものは、紀元前1世紀頃のアレキサンドリアのヘロンが蒸気を噴出させて球を回転させる機械を作っており、ローマ時代には知られていました。
それでも、ローマ時代に産業革命が起こらなかったのは、石油の存在は知られていましたが、化石燃料を文明を動かす動力源として、使わなかったからです。そして、産業革命が起きた時代にはイギリスでは、畜力と人力が石炭に代わっています。一方、ローマのあったイタリアは同時代にも石炭の使用量が増えていないので産業革命は起きていません。
あるエネルギーを投入した場合に、どれだけの見返りが得られるのかをEROI(Energy Return On Investment)と呼びますが、風車はたかだか8、褐炭は30、石炭は100、石油は200もあります。石炭や石油にこれだけエネルギーが濃縮されているのは、過去の数万年分もの光合成エネルギーが長い地質時代の圧力や熱を受けて圧縮されているからです。人力や風力から石炭、石炭から石油へと300年も高いEROIの変化を経験してきたことから、技術によって社会は進歩し、経済が成長するという壮大な神話が産まれました。
ですが、人類は石油に匹敵する濃縮されたエネルギー源を手にしていません。他のエネルギーから作られる水素エネルギーは論外としても、バイオマスにしても産業型のものはマイナスです。
情報だけは例外ではないかという考え方もあります。確かに、パソコンの性能は「ムーアの法則」のように指数関数的に進歩してきています。ですが、現代のサーバー空間は膨大な電力なくしては維持できません。さらに、ダニエル・ベルの「情報化社会論」は、農業や工業がなくなるのではなく、それを開発途上国にアウトソーシングしているだけにすぎません。
ポストカーボン研究所のリチャード・ハインバーグ(Richard Heinberg)は、著書『成長の終わり(The End of Growth)』で、自動車にしても飛行機にしても、画期的な技術は生まれておらず、技術が進歩するとの幻想は、ハイブリッド自動車のようにコンピューター技術の進歩に依存するところが大きいと指摘しています。
- Q. 経済成長を続けることに伴う犠牲はありますか、それは何ですか、なぜ生じるのですか
-
第二次経済が成長する問題点は、その基盤となる第一次経済を蝕んでしまうことです。自然生態系は、一度壊れてしまうと、後から気づいて、あわてて復元しようとしても、もはや取り返しがつかなくなってしまう閾値があります。グローバルに見れば、気候変動、人工窒素、そして、生物多様性の喪失が閾値を超えてしまったと言われています。
生物多様性が重要なのは、キーストーン種ともに、それがレジリアンスの鍵となっているからです。例えば、オオカミを失った生態系ではシカがもう繁殖します。そして、ある日、食料がなくなると絶滅します。これをワシントン州立大学のウィリアム・コットン名誉教授(William Robert Catton、1926年~)は、オーバーシュートと言っています。例えば、天敵がいないベーリング海のセント・マシュー島には1944年に人工的に29頭のトナカイが導入され、1963年は6000頭まで増殖しましたが、食料源である地衣を食べ尽くすと、そのピークとなった3年後にたった42頭にまで激減しました。人間も例外ではありません。
- Q. 日本がこれまで経済成長を続ける中で失ったものがあるとしたら何でしょうか
-
第三次経済の問題は、もともとマネー化されていなかったものをすべてマネー化することによって、経済成長しようとする力が働くことです。タダであった水もペットボトル化し、人間関係もマネー化していく。それは、社会システムとしてのレジリアンスがなくなっていくということです。
社会学者の見田宗介氏は「金がない生活が貧しいのではない。金がないと生活できない社会において金がないことが貧しいことなのである」と指摘しています。経済成長をする中で、日本は、金がなければ生活ができなくなりました。これが決定的だと考えます。
- Q. 「経済成長」と「持続可能で幸せな社会」の関係はどうなっていると考えますか
-
一般的には経済成長と持続可能性とはトレード・オフの関係にあると考えられています。先進国のようにエネルギーを多く使う国は幸せですが地球に環境の負荷をかけます。アフリカのようにつつましく暮らす国は環境許容内で生きていますが、医療、教育等の最低限の福祉基準を満たせません。
ですが、世界野生動物基金のリビング・アース・リポート(2006)によれば、世界ではただ一国、キューバだけが、地球環境に負荷をかけず、同時に国連開発計画の平均寿命、教育水準等の人間開発指標をクリアーしています。このことは国の社会制度のあり方によって、無理に経済成長をしなくても、人間開発指標を満たせることを示唆しています。
さて、1960年代までは「開発・経済成長=幸せ」と考えられてきましたが、教育や医療等、マネー以外の要素が開発指標に取り入れられるようになったのは、チリ出身のユニークなエコノミスト、マンフレッド・マックス=ニーフ(Manfred Max- Neef、1932年~)の影響があります。
ニーフは、人間の欲望は無限ではなく、生存、保護、愛情、理解、参加、閑暇、創造、アイデンティティ、自由の9つしかなく、それは、どの文化でも同じで、かつ、歴史的にも変わらず、文化や時代によって変化するのは、こうしたニーズを満たす手段だけだと考えました。例えば、先進国の女性が最高級のブランド品を購入するのも、先住民の「裸族」の女性が入れ墨をするのも、アイデンティティというニーズを満たすためで同じなのです。ニーフの考え方からすれば、経済成長は9つのニーズを満たす手段にすぎず、このニーズが満たされれば、経済成長しなくても幸せになれることになります。
1970年代以降、先進諸国ではGDPが増加していますが、ある水準を超えると、幸せ感が高まっておらず、むしろ低下していることがわかります。マネー経済を成長させても、むしろ幸せにならないことを最初に指摘したのは、米国のエコノミスト、リチャード・イースターリン(Richard A. Easterlin,1926年~)であることから、「イースターリンのパラドックス」とも言われます。
さて、ニーフは、こうした考え方をラテンアメリカの人々の暮らしから編み出しましたが、いま、ラテンアメリカでは、アンデスやアマゾンの先住民の世界観をベースに「ブエン・ヴィヴィル(Buen Vivir=良く生きる)」という考え方が、成長へのオルタナティブとして登場し、エクアドル憲法(2008年)やボリビア憲法(2009年)にも位置づけられています。
ブエン・ヴィヴィルは、2012年9月にベネチアで開催された「第3回脱成長国際会議」以降、脱成長運動と似た考え方であるとして注目されていますが、私はさらに奥が深いものがあるとしています。
ブエン・ヴィヴィルでは、人間は一人だけでは幸せになれず、社会の中で、コミュニティと調和がとれた関係性が保たれているときにのみ幸せになれると考えます。さらに、ブエン・ヴィヴィルの社会には、人間だけでなく、他の動植物や空や山等の自然も入るのです。ここから、パチャママ(母なる地球)と調和して生きるという概念が産まれています。2010年4月には、ボリビアのコチャバンバで、気候変動と母なる大地の権利の会議が開催されています。
繰り返しになりますが、経済成長とマネー化された生活が世界を席巻し始めたのは、長い人類史ではつい最近のことにすぎません。現在では、マネー化されず贈与経済で生きている人はごく限られていますが、持続可能性内で幸せに生きてきたケースと無理に成長して破綻した対比的な2ケースが太平洋上の絶海の孤島で見られます。イースター島とソロモン諸島に属するアヌタ島です。
かつて、イースター島には豊かな森があり、この森の樹木から丸木舟を作り、海産物を確保していましたが、他の部族よりも大きなモアイ像を建てようと競い合い、ただモアイを移動させるためにすべての樹木を切り倒しました。その結果、土壌は流出し、島の資源では自給できないだけの人々が残されましたが、気を切り倒してしまったために、カヌーを作って島から抜け出す手段もありませんでした。その後には、イースター島では、戦争、飢餓、食人が起こります。
一方、アヌタ島民は、限られた木材資源が貴重だとの文化を発展させ、作ったカヌーは150年以上も家族で大切に使い、鳥、魚 他の野生生物も尊重し、絶滅しない範囲で狩猟してきました。農業も集約的な輪作やアグロフォレストリーを試み、「アロパ(Aropa)」と称される哲学をベースに、不作な家族がいれば食料をわかちあいました。今もアヌタ島では、すべてが無料で贈与経済でわかちあわれているため、マネーがいらず、誰もが、豊かなために隣人と争う必要はないと言います。
コインは、紀元前560年にリュディア(Lydian)王国で発明されて以来、ギリシアでもローマでもインフレと格差拡大という問題を引き起こしてきました。ローマの金融制度は非常に優れていたものでしたが、その経済は軍事略奪と成長がベースとなっていたため限界に達して崩壊します。その後に誕生したヨーロッパ中世社会が、利潤を否定し、農地と労働力をベースとした小さな自給領主権からなる封建システムになったのはその反動です。
紙幣は、中国で発明されましたが、元の時代に銀本位制を捨てたため、凄まじいインフレを引き起こします。その後に誕生した朱元璋の明が、グローバル化を否定し、貨幣を否定し、農民をベースとした小さな自給圏の集合体としての国家を理想としたのもその反動です(永楽帝の時代にまた変貌しますが)。
冒頭で述べたように、第三次経済、現在の法定不換紙幣(fiat money)は、金融危機やバブルの危機を内在化させています。けれども、マネーを用いながら、崩壊することなく、インフレも起こさずに長期にわたって持続した文明があります。古代エジプトです。
古代エジプトのエネルギー源は人間や家畜の筋肉だけでしたが、3000年前の第19王朝のファラオ、ラムセス2世(紀元前 1314頃~紀元前1224年、または紀元前1302頃 ~紀元前1212年)の統治下の庶民の暮らしは、ルイ14世(1638~1715年)時代のフランスの庶民の生活水準に匹敵するものでした。
さて、このラムセスの富は、穀物金融制度によって築かれたと示唆する歴史家もいます。古代エジプトでは、小麦が物品貨幣として使われていました。物品貨幣が機能するためには安定性と信用性が不可欠ですが、ナイルは毎年の着実に洪水によって土壌を供給するため、エジプトの小麦生産は人類史上、最も安定したものでした。さらに、小麦は保管していると腐り、ネズミにも食されて減少するため、シルビオ・ゲゼルのいうマイナスの利子を持つ「減価する貨幣」の機能を着実に果たします。農民たちはマネーを貯めこまず、農地や灌漑システムに投資し、これが、農業を豊かに発展させました。
紀元前330年前後には、小麦貨幣をベースにギリシャの銀行制度を組み合わせ、プトレマイオス王は、完全な銀行ネットワークへと発展させます。この銀行システムは、その精巧さにおいて、2000年後の18世紀のヨーロッパの制度もしのぐものだったと言われます。
小麦をベースとしたエジプトの貨幣制度は1500年以上、銀行システムも、エジプトがローマ人に征服されて制度が放棄されるまで、百年以上も続きましたが、この期間に、銀行が破産したり、インフレが起こった記録は全くないのです。
冒頭のグリアの事例に戻れば、エジプトの経済は、物品貨幣をベースに第三次経済を否定し、第一次経済の上に立脚した健全な第二次経済であったと言えます。
食料に限れば、大型機械と近代品種を用いたモノカルチャーのアグリビジネスは1のエネルギー投入に対して40分の1の産出しか産み出せない非効率なものですが、マネーが価値指標となっているために、経済的に効率のよい農業とされてしまっています。しかし、ピーク・オイルを迎えた今、これから、石油をはじめとした化石燃料は潤沢に使えなくなります。現在、エネルギーは交通、冷暖房、製造に使われていますが、まず、打撃を受けるのが交通です。
第一次経済と第二次経済だけに限れば、日本は森林や水資源に恵まれています。米という物品貨幣をベースに、世界的にも稀に見る持続可能な豊かな文化を育んできた江戸社会の事例もあります。
そして、石油や原発に頼らず、持続可能な暮らしを実現するためのテクノロジーもすでに手にされています。
もし、人々が破滅することなく生き延びていられるとすれば、ピーク・オイルが本格化すれば、グローバル貿易は過去の物語となり、地産池消をベースに20世紀文明が残したプラスの遺産、鉄やガラス等を修理しつつ活用し、同時にマイナスの遺産、放射性廃棄物や化学廃棄物に悩みつつ、アグロエコロジーやパッシブソーラーハウス等、身の丈にあった技術を利用しながら、それなりに幸せに生きていくに違いありません。ただ、問題は、そうしたオルタナティブの実験を現在のマネー経済が許さないことです。贈与経済と物品貨幣をベースとした地域経済をどのように作っていくのかがひとつのポイントとなると思います。
インタビューを終えて
『江戸・キューバに学ぶ"真"の持続型社会』という本を、江戸の研究家である石川英輔先生など5人で一緒に書いた吉田太郎さんにインタビューに答えていただきました。
この内容からもわかるように、吉田さんは非常に幅広く読書・勉強していらっしゃる方で、また何度もキューバを訪問し、『「没落先進国」キューバを日本が手本にしたいわけ』をはじめ、キューバから日本が何を学べるか、学ぶ必要があるかに関する書籍を何冊も出しています。
今回のインタビューでもいろいろなことを教えていただきました。「国内総生産(GDP)を第一次、第二次、第三次の経済に分類する」という考え方と試みは大変に興味深く、重要ですね! 日本ではどうなるのでしょうね?
チリの経済学者、マックス・ニーフの考え方からすれば、「経済成長は9つのニーズを満たす手段にすぎず、このニーズが満たされれば、経済成長しなくても幸せになれることになります」という点も希望を与えてくれます。そして、ラテンアメリカでの成長へのオルタナティブ「ブエン・ヴィヴィル」、もっと知りたい! 伝えたい!と思いました。今回もいろいろな学びをありがとうございました。
取材日:2015年4月15日
あなたはどのように考えますか?
さて、あなたはどのように考えますか? よろしければ「7つの問い」へのあなたご自身のお考えをお聞かせ下さい。今後の展開に活用させていただきます。問い合わせフォームもしくは、メールでお送りください。
![]()