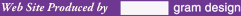2011.06.03
東日本大震災の被災地・石巻で考えた「自然との共生」ということ

Photo by Junko Edahiro
ジャパン・フォー・サステナビリティ(JFS)ニュースレター No.105 (2011年5月号)より
http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/030978.html
3月11日に起きた東日本大震災は、地震と津波によって1万5000人を超える死者と、今なお1万人近くの行方不明者を出す大惨事を引き起こしました。4月29日から5月10日まで、最も被害の大きかった地域の1つである宮城県石巻市に入り、被災地支援を展開する国際協力NGOジェン(JEN)の現地事務所でお手伝いをしてきました。
宮城県第2の都市である石巻市の人口は約16万人。今回の震災で3,000人近くの命が失われ、多くの家屋が津波に流されました。震災後2か月たった今も、人口の5%近くにあたる8,000人を超える人々が市内の100か所を超える避難所で暮らしています。
東京から新幹線で2時間の仙台からバスに乗り換えます。仙台~石巻を結ぶ仙石線は震災によって大きな被害を受けており、完全復旧には数年かかるのではないかとも言われています。高速バスで1時間半ほど走って、石巻市内に入ると、それまでの「日常の風景」が一変しました。道の両側に、津波の水につかって使えなくなってしまった家具や家電製品、畳や布団、その他たくさんのものが山積みにされています。海から数キロの地点まで津波が押し寄せたのです。家は倒れずに立っていますが、1階は住めない状態になっている家も多いようです。
石巻駅からジェンの現地事務所まで、タクシーに乗りました。私は何も聞かなかったのですが、初老の運転手さんは、被災して小学校の避難所で暮らしている、まさか自分の家まで津波が来ると思わなかった、最初の10日間は避難所にすし詰め状態で、横になって寝ることもできなかった、家は住めなくなり、立て直すお金もなく、仮設住宅もすごい倍率だしずっといられるわけではないし、行くところがない、自分のまわりでも知っている人がずいぶん亡くなった、命が助かってよかったとみな言うが......死ぬときは一瞬苦しいと思うが、生き残ってしまった人間はあれもこれも悩まなくてはならない、どちらがよかったのかと思う......と、ぽつりぽつりと悲しい話をしてくれました。
ジェンの事務所から車に乗り、海辺の地区に入った時、言葉を失いました。どこまで走っても、見渡す限りがれきの山が続いています。少し前までだれかのお家を構成した柱や板、家具、そのほか多くのものが破壊され、泥だらけになって、そのままになっているのです。自動車もあちこちで、骨組みだけになったり、ひっくり返ったりしたまま。窓に「捜索済み」という紙が貼ってあるのが見えます。車椅子がひっくり返っています。ぬいぐるみが泥の中から顔を出しています。
何か所か避難所にも行きました。ある小学校の体育館では、ダンボールで仕切った一人当たり数平方メートルほどの空間がそれぞれの避難者の"仮の住まい"になっています。食事は自衛隊の炊き出しや、市から配布されたり、全国から支援物資として寄せられるパン、カップ麺、お弁当などです。避難所によっては、自分たちで順番を決めて調理をしているところもありますが、全般的に野菜不足など栄養が偏っていることが心配されています。
このような避難所だけではなく、親せきや知り合いのところに身を寄せている人も多く、石巻だけでも1万戸の仮設住宅が必要とされていますが、土地の確保などがなかなか進まず、4月末時点で建設が計画・進行しているのはまだ1,800戸ちょっとでした。仮設住宅の建設は、国が資材の調達を、市町村が土地の確保を、県が建設を担当するといった形で分担が決まっていますが、スムーズな調整のもと、一刻も早く希望者全員が仮設住宅に入れることを祈っています。
今回、被災地のあちこちを見たり、人々に話を聞いたりする中で、さまざまなことを考えさせられました。その1つが「自然との共生」ということです。日本は地震国です。地震に伴う大津波も、過去にも何度も経験しています。また、年によっては1年に10もの台風が上陸する台風国でもあります。モンスーン気候帯に属し、急峻な山林が国土の70%近くを占めるなど、大雨による洪水や土砂崩れなどの自然災害の起こりやすい国です。
石巻には、頑丈な護岸堤防がありました。市も人々も安全だと信じていました。しかし、今回の津波はその堤防をやすやすと超え、市内をめちゃくちゃに破壊し、大きな被害を出したのです。地震や津波という自然の脅威の前に、人間や人間がつくったものがいかにもろいかということを痛感しました。
私たちはよく「自然との共生」という言葉を使います。企業のCSRレポートなどにもよく登場しますし、町づくりの議論には必ず出てくる言葉です。でも、これまで私たちが使ってきた「自然との共生」とは、とても薄っぺらくて、甘いものだったのじゃないか? と思いました。まるで「箱庭」か何かのように、自分たちに襲いかかってくることのない、自分たちが愛でる対象としての自然を近くに配することを「自然との共生」と言ってきたのではないか、と。
石巻をはじめ、ほとんどの町づくりは、「津波が来ても大丈夫という、頑丈な堤防を造る」という、人間の工学で自然の脅威を抑え込むという発想が基盤になっています。しかし今回の津波は、人間の工学の想定以上の強さだったので、うまくいきませんでした。では次にはどうしたらよいのでしょうか? もっと強くもっと高い堤防を造ればよいのでしょうか? 釜石市でも、堤防を乗り越えて津波が押し寄せ、大きな被害を出しました。以前にこの地を襲ったチリ地震津波を教訓にして建てた巨大な堤防だったのですが。
一方で、今回大きな被害を受けた岩手県宮古市でも、姉吉地区にいた住民は全員が無事でした。姉吉地区は1896年の明治三陸大津波、1933年の昭和三陸津波のとき、集落がほぼ全滅する被害を受けました。生存者はそれぞれ2人と4人だったといいます。この地区の海岸から約500メートルの山道に、「高き住居は児孫の和楽 想え惨禍の大津浪」と始まる石碑が建っています。「津波はここまで来た」「ここより下に家を建てるな」「幾年経るとも用心あれ」と刻まれた警告を、集落の人々は守り続けてきました。集落全戸が石碑よりも内陸側に建てられていたため、今回の津波で人命にも家屋にも被害はなかったそうです。
昔から、アジアのモンスーン地帯には「氾濫原」がありました。台風など大雨が降ると、洪水が起き、川の水が氾濫します。しかし、その氾濫のおかげで上流からの栄養が土地に行きわたり、その後の農作物の収穫を支えてくれるのだから、氾濫をむりに止めるのではなく、ときどき川が氾濫するだけの余地を「氾濫原」として置き、もともとはそこには人は住まないことになっていたといいます。自然の揺らぎにあわせて人間のほうが身を引いていたのです。
人口が増加し、「お金を払えばどこに家を建てても勝手だろう」という風潮が広がるにつれ、氾濫原に家が建てられるようになり、台風や洪水の被害が大きくなったとも言われます。そういう川の近くに住みながら、高い堤防など工学に自然の脅威を抑え込むものを求めるようになります。
「生かされている」という、日本もしくは東洋の考え方があります。生きとし生けるものだけではなく、命のないものも含めて、あらゆるものがつながってあみだす網の目の一つの部分として自分が存在しているという意味合いです。
老荘思想は、天(宇宙)の大もとのあり方――それをこちらが操作しようとか、抵抗しようとかするのではなく――に、自分のあり方を合わせていくのがいちばんスムーズな生き方だという考え方ですが、それを代表する概念が「無為自然」です。
家をすべて流されて、避難所になっている地元のお寺で、高齢者など数十人の避難者のお世話役をしながら暮らしている女性が、「海が大好きなんです。津波が来て、家は流されましたが、仕方ないと思っています。テレビでは、海に裏切られたとか海を恨んでいるとか言いますが、自分はそんなふうには思ったことはありません。海が好きで海の近くに住んでいるのだから、仕方ない。また海のそばに住みます。今度はもうちょっと高いところに住もうと思っていますけど」と話してくれた時、この言葉を思い出したのでした。
無為自然の「自然」は「自ずと然り」という意味ですが、老荘思想では、そのためには無為が大事だと説きます。「無為」の逆は「人為」です。人が何かをしてコントロールしようとすることです。工学的な技術を持って津波を抑えようとか、洪水を抑えようとすることは人為です。
私たち人間は、自然を抑え込むべき対象としてみるべきなのでしょうか。それともそのゆらぎに自らの身を任せるのでしょうか。今回の震災は、私たち人間と自然との関係性や距離感を再考させる大きな機会になりました。
石巻をはじめ、被災地では「地域の復興・町づくり」に向けた話し合いや取り組みが始まっています。「より高くて強い堤防を」という町づくりになるのか、今回の津波の記憶と「ここから先は自然の領域なのだから、住んではいけない」という学びを未来へ伝えていく町づくりになるのか。1つの正解があるわけではないでしょう。しかし、これからの町づくりでは、短期的な効率だけではなく、中長期的なしなやかな強さ(復元力、レジリアンス)を高めることも重視してほしい――そう強く願っています。