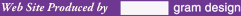レジリエンス向上の取り組み
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則7 多元的なガバナンス・システムの促進
 Photo by Matthew Osborn on Unsplash
Photo by Matthew Osborn on Unsplash
多元的ガバナンスとは、特定の政策分野や場所で、ガバナンスの主体となる多数の組織が交流して、規則を策定・施行するガバナンス・システムである。かく乱や変化に直面したときに共同行動を実現するための最善策の一つであると考えられている。
共同行動の実現を可能にする方法は数多くあるが、多元的ガバナンスに匹敵するものはないと考えられている。社会・生態系システムの持続可能なガバナンスに関する古典的な研究では、いわゆ「入れ子型制度」(人の交流を決定づける規範や規則)が重要視されている。これは、一連の規則で結ばれた制度であり、その規則は空間的・時間的スケールや組織構造の区別なく相互に作用するので、適切な担当者が適切なタイミングで素早く問題に対処できる。入れ子型制度であれば、対処すべき問題に対して「適切」に対応できる社会規範や共同行動を生み出すことが可能だ。
一元的傾向の強い戦略とは対照的に、多元的なガバナンスは、六つの方法で生態系サービスのレジリエンスを高めると考えられている。その六つの方法は、本文書で取り上げたほかの原則と見事に一致している。具体的には、「学習と実験の機会を提供する」、「より広範な参加を可能にする」、「つながりを向上させる」、「モジュール性を生み出す」、「反応の多様性の可能性を向上させる」、「ガバナンスのエラーを最小限に抑制し、是正することが可能な冗長性を構築する」である。
多元的なガバナンスの方が社会・生態系システムと生態系サービスのガバナンスに適している理由には、昔から地元にある知識が尊重される可能性がさらに高まることも挙げられる。その結果、文化やスケールを越えて知識や学習の共有が進む。これは特に地方や地域の水に関するガバナンスで顕著に見られる。例えば、南アフリカの流域管理グループや、フィリピンの大規模灌漑システムの管理では、多元的アプローチを活用し、多様な主体(アクター)の参加と昔からある地元の科学的な知識の導入が促進されてきた。
とはいえ、多元的思考の活用を訴えても、使い方の原則が明確でなければ実現できない。空間的・時間的スケールを横断した協働プロジェクトにはさまざまな取り組みの事例がいくつかあるが、そうした取り組みがガバナンスに与える影響を分析したものはほとんどない。多元的ガバナンスには課題も三つある。そのどれもが生態系サービスのレジリエンスを強めるどころか弱める可能性のある課題だ。第一に、冗長性や実験と、多数のガバナンス組織や利害関係者を関与させるためのコストとのバランスを取る必要性だ。例えば、南アフリカの国家水利法は、総合的な水源管理を提唱し、各組織に適したものにするためその改善に取り組んでいるが、一方で、規模とコストのバランスを取らなければならないという現実も認識している。第二の課題は、生態系サービスのさまざまな利用者の間で生じるトレードオフを避けるというものだ。こうしたトレードオフは第三の課題につながる場合が多い。その第三の課題は、政治的な対立や、共有資源が偏った利益をもたらす可能性といった問題の解決に対処することだけでなく、いわゆる「スケールあさり」にも関係している。これは、あるスケールの政策に不満を抱えたグループが、自分たちの利益を生むという理由だけで、より都合が良い政治の場に近づく行為だ。
主要メッセージ
組織やスケールを越えて協働できると、スケールと文化を越えたつながりや学習が向上する。ガバナンス組織間のつながりがよいと、適切な人材が適切なタイミングで対処できるため、変化やかく乱が起きても迅速に対応できる。
事例研究
アリゾナ州南部の環境管理
アリゾナ州南部では、環境管理や生態系サービスの促進に関する協働プロジェクトが数多くあり、どれも多元的システムとして見なすことが可能だ。同州のコチセ郡では、20を超えるグループや主体(アクター)がこの地域の切迫した環境問題に関する意思決定プロセスに携わっている。協働プロジェクトのタイプは、単に情報を共有するという小さなものから、より緊密に結びついた協働ネットワークまでさまざまだ。例えば、ノーザン・ジャガー・プロジェクト(Northern Jaguar Project)もチリカワ・ファイアースケープ(Chiricahua Firescape)も、情報を共有し、多様な主体(アクター)を結び付ける非公式のネットワークを構築している。アッパー・サンペドロ・パートナーシップ(Upper San Pedro Partnership)はさらに踏み込み、モニタリングと共同投資の調整を行っている。多元的システムの成功例といえばマルパイ・ボーダーランド(Malpai Borderlands)だろう。ここは、堅い絆で結ばれたグループで、放牧地の状態のモニタリングを目的として数十年かけて信頼関係を築き上げてきた。こうした協働プロジェクトやネットワークは、統合的に、環境問題の取り組みに対する多元的管理アプローチに役立っている。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-7/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則6 参加の拡大
 Photo by Dylan Gillis on Unsplash
Photo by Dylan Gillis on Unsplash
すべてのステークホルダーが積極的にかかわり合いながら参加することは、社会・生態システムのレジリエンスを構築するための基本と考えられている。それは、意思決定の過程において、知識と権威の正当性を高めるために必要とされる信頼と関係性を構築する上で役に立つ。
多様なステークホルダーが社会・生態系システムの管理にかかわると、正当性が高まり、知識の深化や多様化が進み、不安要素がある場合はその検知・分析が促進される。その結果、レジリエンスの構築に役立つ。参加には、ステークホルダーへの単なる情報提供から、権限の完全な移行までさまざまな形がある。管理プロセスではいろいろな段階(あるいは、すべての段階)で参加が可能だが、参加者の多様性が特に役立つのは始動時といえよう。というのも、初期段階で参加すると、管理上の優先事項や必要事項を決める際に、利用者グループの知識を組み込むことができるからだ。
参加者の層が厚く、参加がうまく機能していると、さまざまな利点がある。知識があり、うまく機能しているグループには、信頼と共通の理解を構築する潜在性がある――この二つは集団行動の基本となる要素だ。その一つが、オーストラリアの例である。ここでは、グレートバリアリーフの脅威への認識を深めようと、幅広い市民参加とコンサルティングのプロセスが始められた。グレートバリアリーフが直面している脅威への認識がより高まり、これを通じて、市民参加のプロセスは保全計画の改善に対する市民からの支援を拡大することができた。
多様な経験や考え方を持つさまざまな人々が参加すると、これまでの科学的プロセスでは得られなかったであろう考え方が見いだされる場合がある。また、参加が、情報収集と意思決定とのつながりを強化するのに役立つこともある。例えばフィリピンでは、サンゴ礁保護区域で参加型のモニタリングを実施したところ、意思決定の透明性が高まり、その結果、プロジェクトに参加したステークホルダー同士の関係が強まった。また、情報の理解度と妥当性、さらには、意思決定で地元の人々が情報を利用する方法にも改善が見られた。
しかしながら、参加すればよいというわけではない。よく考えて行わなければ、システム内で一部のステークホルダーが力や影響を強めることによって、他者を犠牲にして大きな力を持つようになり、その結果、競争や対立さえ生じかねない。さらには、参加しても資源を利用する地元の人たちにはほとんど権限がなく、責任だけが大きくなるような弱い共同管理の場合、社会・生態系システムのレジリエンスやそれが生み出す生態系システムのサービスの質が低下することもあり得る。例えばチリの漁業では、正式に承認された共同管理の組織が、それまで強い影響力を持っていた地元の資源管理組織を弱体化させた。共同管理組織の目的は、政府が掲げる漁業保護の目標を高めることであったにもかかわらず、その代わりに、資源利用者と資源との間に官僚という層を増やす結果になった。これによって、資源基盤の変化に素早く対応する地元の能力が弱まったのだ。
どうすれば参加を拡大できるのか?
質の高い参加プロセスをつくることは個々の事情に大きく左右されるものであり、誰が参加すべきなのか、使用すべき最適なツールや方法が何なのかを判断するのは難しい。参加型プロセスの実施で陥りやすい失敗には、参加を成功させるために必要な資金・時間・人材を低く見積もること、コミュニケーションや段取りのスキルがしっかり身についていないこと、参加の役割やルールが明確になっていないこと、有意義な影響を与えるにはステークホルダーがプロセスに参加するタイミングが遅過ぎることなどが挙げられる。
より効果的に参加できるようにするためには、いくつかの共通するガイドラインがある。
・参加プロセスに関して目標と期待する事項を明確化する
・適切な参加者を選ぶ
・集団を動かすことができて、熱心でやる気のあるリーダーを見つける
・組織的な能力向上を実現する
・権力の問題や潜在的な対立に対応する
・効果的な参加を可能にする十分な資源を確保する
主要メッセージ
参加は、参加者の層が厚く、うまく機能していると、信頼の構築や、共通理解の創出、それまでの科学的プロセスでは得られないような視野を開くことを可能にする。
事例研究
ソロモン諸島の遠隔地域カフアにおける脆弱性評価
多様な生態系を持つ遠隔地域カフア(ソロモン諸島)は人口が4,500人で、輸送や通信などの手段が限られた40のコミュニティがある。コミュニティは、根菜作物による零細農業、漁業、森林資源に依存している。地元の草の根団体であるカフア協会(the Kahua Association)が、コミュニティの参加や学習、行動のモデルとなる先例を作った。このプロジェクトの参加にはアプローチが3層あり、各層は、参加者のタイプとかかわり方に基づき、研究チームがカフア協会と共同で考案したものだ。プロジェクトはどの段階でも、参加者、ひいてはコミュニティが共に学ぶことを促進し、それが定着するように考えられていた。これは、協会のメンバーが、研究とその結果に関して、企画から共同所有、実施、利用まで、研究のパートナーとして携わったことで可能になった。例えば、社会・環境調査を行うために地元住民を訓練したり、個々の住民に自らの考え方や経験、行動を振り返るよう促したり、コミュニティ内で研究結果を公開し、時宜を得て共有していたなどである。このプロセスの成果として挙げられたのは、コミュニティの参加やデータ収集、発表の広がりなどである。また、レジリエンス構築の基本要素であるリフレクション(振り返り)と学習という文化も培われた。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-6/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則5 学習の奨励

Photo by Kristin Hoel on Unsplash
学習の奨励システムに関する知識は常に断片的で不完全なものであり、社会・生態系システムもその例外ではない。よって、社会・生態系システムのレジリエンスを強化する取り組みには、継続的な学習と実験が必要となる。
レジリエンスとは、変化に応じて適応し、変容していくことである。社会・生態系システムは常に発展しているため、変化に適応させ、管理に取り組めるよう既存の知識を絶えず見直しておくことが必要だ。「適応型管理」「適応型協働管理」「適応型ガバナンス」ではいずれも、意思決定に欠かせない要素として学習に重点を置くとともに、知識が不完全なものであることや、不確実性や変化、予期せぬことが、社会・生態系システムを管理する上で重要な役割を果たす部分があることを踏まえて戦略を立てている。
適応型管理では、社会・生態系システムの働きの仕組みについて、新たな仮説を立て、それがどういうものか明確に示し、それを検証したり、評価したりすることが重要な作業となる。従って、適応型管理とは、管理のための代替アプローチの検証を通じて、実践によって学習することなのだ。
適応型協働管理においても実践による学習に目を向けているが、より明確に重視しているのが異なる主体(アクター)間の知識の共有である。これは地域社会と政策決定機関の間で行われることが多い。適応型ガバナンスでは、さまざまな組織や機関の橋渡しをするために、垣根を越えた知識の共有を通して、学習を促すことに重点を置いている。この組織・機関を横断した学習重視の取り組みを進める目的は、新たな社会通念と協力体制をつくり出すことである。
専門機関や科学者は、しばしばモニタリングや実験を行い、その過程で学習する。しかし、社会の中のさまざまなグループ間での学習を活性化するためには、幅広い人たちの参加が重要であるという認識が高まりつつある。また、異なるグループが協力すればするほど、種々の生態系サービスの価値がより明確になることもあり得る。非常によく知られた事例の一つが、スウェーデン南部の湿地帯クリスチャンスタード・ヴァッセンリッケでの取り組みだ。土壌が水に浸かった価値の低い沼地と見なされていたこの広大な土地は、高まる開発の波が押し寄せて環境悪化が進んでいた。しかし、地元住民や政治家を含むさまざまな人々が協力して管理してきたことが奏功し、この湿地に対する見方が一変した。レクリエーションの場になるなど利用目的が広がり、今では価値の高い土地と考えられている。
同様の例がオーストラリアのグレートバリアリーフだ。かつて政治家や一般の人々の間でグレートバリアリーフは無傷のサンゴ礁だと考えられていたが、今や深刻な荒廃の脅威にさらされていると認識されている。このように人々の見方が変わったことが、サンゴ礁とそれに関連する生態系サービスの保全対策の強化につながった。この二つの例で見られた認識の変化をもたらしたのが協働学習のプロセスである。
どうすれば学習を奨励できるだろうか?
レジリエンスを構築するための学習を促すガイドラインには共通点がある。最も重要なガイドラインは下記の通りである。
・社会・生態系の重要な構成要素に対する長期モニタリングを支援する
・参加者間のかかわりを広げる交流の機会を提供する
・多様な人々の参加を促す
・知識の共有が進む適切な社会的環境を築く
・学習プロセスを行えるようリソースを十分に確保する
・人脈づくりと実践できるコミュニティづくりを可能にする
学習プロセスの設計は重要である。だからこそ、学習を台無しにする状況や障害を考慮に入れておくことが不可欠だ。適応性もしくは実用性のない学習は、社会・生態系システム全体の機能を脅かす方策や行為につながることもあり得る。例えば、ナオミ・オレスケスとエリック・コンウェイの共著『邦題:世界を騙し続ける科学者たち』(Merchants of Doubt, 2011)に書かれている組織的な反環境運動には、環境科学の不確実性を強調したり、「論争」を生み出したりすることで、環境科学を根底から揺るがそうとする思惑がある。
権力の力学も学習の行われ方に影響を及ぼす可能性がある。とりわけ昔から伝わる知識や地域特有の知識をないがしろにするなど、学習や管理を行う上で、科学的知識の方がほかで得られた知識よりも優先される例が数多く見られる。それを象徴する事例がカナダのタラ漁の崩壊だ。地元の漁師がタラの生息数について強い懸念を示していたにもかかわらず、それが無視されていたのだ。
主要メッセージ
適応・協働型の管理を通じた学習と実験は、社会・生態系システムのレジリエンス構築にとって重要な方法である。こうした手段を講じることで、解決策を考え出す際に多彩な種類の知識や多様な源から得た知識が確実に評価や考慮に入れられるようになるとともに、より進んで実験を行い、リスクを厭わないようになる。
事例研究
米国南東部における火災管理の社会的学習
かつて米国南東部にはダイオウマツが自生するサバンナが広がっていた。このサバンナの生態系は火入れによって保たれていたが、林業や農業、火災発生の抑制によって、今では以前の範囲の数パーセントにまで縮小している。数多くの絶滅危惧種の生息地であり、無数の生態系サービスを提供しているこの生態系を維持する上で、重要な鍵となるのが火災の管理である。そこで、自然保護団体ザ・ネイチャー・コンサーバンシーとエグリン空軍基地(ダイオウマツのサバンナが最も広く残る施設)は適応型管理のパートナーシップを結び、参加型のモデリング手法を用いて、長期間の森林ダイナミクスの統合モデルを開発し、火災管理の代替策を評価した。
5年にわたるこの学習プロセスによって、過去と現在の森林火災のダイナミクスについて新たな理解が得られた。その中の重要な発見は、森林地帯はもっと頻繁に燃やされる必要があること、古い林を保護するために講じられていた対策は害のほうが大きいこと、火災と植生のフィードバックを考慮に入れた政策によって計画的に火災を起こす処置の効果を大いに高める可能性があることだった。火災に伴う植生のダイナミクスを明確に理解できる単純なモデルと、将来の道筋をつくったことで、このプロセスで得られた理解を新たな政策と実践に変えることができた。その結果、火災を管理するだけでなく、ダイオウマツのサバンナを保全・拡大するための新たな生態系管理政策の策定や意思決定に役立つツールの開発につながったのである。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-5/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則4 複雑で適応型のシステム思考の育成

Photo by Dimitry Ljasuk on Unsplash
私たちがさまざまな生態系サービスから恩恵を受け続けるためには、社会・生態系システム内における主体(アクター)と生態系との間の複雑な相互作用とダイナミクスを理解する必要がある。「複雑で適応型のシステム思考」では、こうした相互作用とそれらが生み出す、しばしば複雑な動きをするダイナミクスを評価しており、この思考に基づいた管理をすれば、社会・生態系システムのレジリエンスを高めることができる。
私たちを取り巻く世界の複雑さがより明確になるにつれ、その中での行動の仕方についての理解も変化している。現在、幅広い分野の研究者たちが、差し迫った今の社会・生態系に関する課題の理解と解決に欠かせないものとして複雑系思考の議論をし、それを取り入れ、支持している。しかしながら、人々の準拠枠の変化を促すことは、単に知識基盤を増強するだけの話ではない。それは、人々の考え方と行動を変えることになるのだ。
複雑で適応型のシステム(CAS思考)のアプローチは、還元主義的思考とは一線を画し、社会・生態系システム内で、いくつものつながりがさまざまなレベルで同時に生まれていることを容認するものだ。さらに、複雑系思考とは、予測不能性と不確実性を受け入れ、多様な視点を認める考え方のことである。
社会・生態系システムを理解するためには、システム内の主体(アクター)がどのように考えるか、そして、彼らがとる行動には「メンタルモデル」がどう影響するかを理解する必要がある。メンタルモデルとは、推理・意思決定・行動の拠り所になる認知構造である。つまり、主体(アクター)がどのようにシステムを理解しているか、そしてそれをいかに管理し、システム内での変化にどう対応しているか、について洞察するということである。今日、管理者の間では、一つの問題に対する決まった公式や万能の解決法などは存在し得ないという認識が高まっている。CAS思考がシステムのレジリエンスを直接高めている例証は限られてはいるものの、その向上に貢献していることを示す例はいくつかある。その一つが、南アフリカのクルーガー国立公園の例だ。そこでは、管理者は、ゾウの個体数や火事の頻度といった生態系の状態を一定の水準に維持する戦略をやめて、代わりに境界を定め、その範囲内なら変動を認めるという管理方法を採用している。閾値指標を利用することで、システムの構成要素(例:ゾウの個体数)が危険値に近づいてくると、管理者に警戒信号が伝わるようになっている。この管理手法の総体的な狙いは、人間の介入(および投資)を減らし、生態系と生息地の種類の多様性を拡大することにある。
どうすればCAS思考を育成できるだろうか?
CAS思考は、以下のガイドラインに基づいたさまざまなやり方で展開・育成・利用ができる。
システムの枠組みを導入する
そうすれば、人々が考えをまとめ、人間と環境との間の相互依存と関係性の理解を明確にするのに役立つ可能性がある。
変化と不確実性を予測し説明する
それは、代替となる発展の道を探索・検討し、意図したものも予期せぬものを含め、さまざまな決定の結果を評価するためのシナリオ・プランニングのような構造化されたプロセスを用いることによって可能となる。CAS思考を促進する共同プロセスは、レジリエンスのあるシステムを育成できる見込みが高い。多様で体系的な参加型方式は、それぞれ異なる利害や知識を持つさまざまなグループを引き入れるのに有効だろう。
重大な閾値と非直線性を詳しく調べる
閾値を超えると、社会・生態系システムを管理する上で重大な影響が生じる。従って、管理者が確固たる目的や計画性を持ってシステムの境界と閾値について熟慮することが極めて重要である。
社会の諸制度を社会・生態系システムのプロセスに合わせる
そのようにすると、管理の仕方が従来の資源ごとの管理から、より統合された社会・生態系システムの管理に移行するため、制度の変更や、責任と専門的知識についての見直しが行われるかもしれない。
認知変化の妨げとなるものを見抜く
システムの既存のレジームから恩恵を受けている人々は、この思考の採用に抵抗を示す可能性がある。それは、CAS思考が自分たちの立場を脅かしかねない、驚くような新しい要素の受け入れを助長するのではないかと恐れるためだ。
主要メッセージ
CAS思考はシステムのレジリエンスを直接高めるものではないが、社会・生態系システムがつながりと相互依存という予測不能で複雑な網目の上に築かれているという認識は、レジリエンスを育成できる管理行動の最初の一歩になる。
事例研究
ティサ川流域の新しい河川管理
欧州のティサ川流域の管理パラダイムの進化は、CAS思考が河川管理に対するアプローチの変革をどのようにサポートしてきたかを示す一例である。山岳流域と平らに広がる氾濫原を持つティサ川は、欧州で非常に極端な水位変動が起こると被害を受けやすいが、工業や農業を支える堤防や排水路といったシステムによってそれがいっそう深刻化している。1990年代後半には、洪水やランドスケープの変化、そして生物多様性の喪失が危険なレベルに達し、それがきっかけで科学者や地元の活動家が影(非公式)のネットワークを組織し、河川管理の代替策に関する意見交換を行うようになった。そのネットワークは、組織・機関横断型の推進力や不確実性、河川管理に多様な視点を取り入れることの重要性を認めるCAS思考の理解を進めるために、参加型科学を利用した。さらに影のネットワークは、参加型のシステム・ダイナミクス・モデルのツールを利用し、これまで河川管理で重視されていた物資の輸送と洪水の緩和から、生物多様性と持続可能な土地管理方法の維持を重視するものへと転換するため、それに必要な要素を把握しようと努めた。こうして、参加型の討論会が、共有されたCAS思考を発展させる鍵となり、治水政策における実験を推し進めた。しかし、影のネットワークがCAS思考に基づくアプローチを取り入れたにもかかわらず、政策は一時的にしか変わっておらず、政策の実施が行き詰まった際には、CAS思考の適用における障害が浮き彫りになる。従って、CAS思考によるアプローチは、共通の理解を構築し、社会資本を生み出す一助にはなっているが、ティサ川のシステムにおいて河川管理方法に変革をもたらすところまでには至っていない。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-4/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則3 緩やかに変化する変数とフィードバックの管理

Photo by Claudia Chiavazza on Unsplash
社会・生態系システムは、大抵の場合、多種多様な形に「構成される」ことが可能だ。つまり、システム内のすべての変数が互いにつながり合って相互作用できる形はたくさんあり、こうした構成の違いがさまざまな生態系サービスを提供している。
いつでも利用可能な飲用水を提供してくれる淡水湖のような生態系を想像してみよう。その湖の水質は、沈殿物中のリン濃度といった緩やかに変化する変数と関連があり、次にそうした変数は湖への肥料の流出と関連してくる。社会的領域では、法律制度や価値観、伝統も、緩やかに変化する重要な変数となる可能性がある。それらは、例えば、湖周辺の農地でいつ、どれくらい肥料を使用するかといった農業のやり方を通して、既存の生態系サービスに影響を及ぼすこともある。
フィードバックとは、変数同士をつなぐ双方向型の「コネクター」であり、変化を強めたり(正のフィードバック)、あるいは変化を抑制したりすること(負のフィードバック)ができる。強化型のフィードバックには、ハワイに持ち込まれた草が火災の原因となり、火災が草のさらなる成長を助長し、自生の灌木種の成長を抑制したという事例がある。草がはびこれば、火災も増え、今度はそれが草のさらなる増殖につながる。これが自己強化型フィードバック・ループとなる。また、抑制型のフィードバックの例には、規則違反に対して課される、公式あるいは非公式の制裁や処罰がある。適切な処罰は、違反者の不正行為の再発を防ぎ、将来ほかの人が不正行為をしようとするのを思いとどまらせることができる。
どうすれば緩やかに変化する変数とフィードバックはレジリエンスを高めることができるだろうか?
社会・生態系システムは、適応性のある複雑なシステム、すなわち、洪水や都市部への人々の移住などのかく乱や変化に対応して、調整・再編成ができる自己組織化されたシステムである。ほとんどの場合、抑制型のフィードバックがかく乱や変化の影響力を弱めるのに役立つため、システムは回復して元通りの働きを維持しながら、変わらない一連の生態系サービスを生み出すことができる。
その一例として、浅い湖で澄んでいた水が藻類に埋め尽くされてしまうまでの推移がある。通常、きれいな浅い湖の底には固着性植物が多く生育している。これらの植物は、湖周辺の流域にある開発された農地や都市によって流出するリンや窒素を吸収し、水をきれいに保つのに役立っている。つまり、こうした植物は栄養素汚染の影響を緩和する抑制型のフィードバックを提供しているのだ。しかし、システムがかく乱や変化にさらされるのにも限界があり、その限界を過ぎると、抑制型のフィードバックは大打撃を受ける。そうすると、システム内では、壊れるフィードバックも現れ、一方で新たなフィードバックのつながりが形成される可能性も出てくる。そして、システムは違う形で構成され、異なる一連の生態系サービスを生み出すことになる。湖の場合、周辺地域での農業の拡大によって、最終的には湖水内のリンや窒素の濃度(緩やかに変化する変数)が植物の吸収能力を超えるという結果になるかもしれない。いったんこの閾値を超えると、水中で増え過ぎた栄養素が浮遊性の藻類を成長させる。次に、藻類が水中に届く光の量を減らし、徐々に、固着性植物の死滅、ひいてはそれらが提供していた抑制型のフィードバックの喪失という事態につながっていく。通常、「きれいな水のレジーム(生態系が維持している構造や機能)を元通りにするためには、人の手で藻類を繰り返し取り除き、栄養素の流出をレジームの移行(レジーム・シフト)が起こる前の状態よりもずっと低いレベルにまで減らす必要がある。そうしてようやく、固着性植物が自ら再生して「きれいな水のレジーム」の再形成に貢献する可能性が出てくる。
どうすれば緩やかに変化する変数とフィードバックをうまく管理できるだろうか?
緩やかに変化する変数とフィードバックを管理する際に重要なことは、望ましい生態系サービスを生み出す社会・生態系のレジームを維持するそれらの変数とフィードバックの中で、主要なものを特定し、さらにシステムの再構成につながりかねない重大な閾値のあり場所を突き止めることである。たとえ一時的なものであっても、いったんそれが分かると、以下のガイドラインを適用することが可能になる。
望ましいレジームを持続させるフィードバックを強化する
例えば、ハードコーラルのサンゴ礁は、漁場やエコツーリズムのような生態系サービスを提供するが、気候変動や漁業のようなストレスが原因で、その生態系を海藻がはびこるレジームへと一変させる場合がある。しかし、ハードコーラルのサンゴ礁のレジリエンスは、海藻を食べることによって抑制型のフィードバックをもたらすブダイのような草食魚類の個体数を増やすことで、高めることが可能である。魚の乱獲を防止し、サンゴ礁の利用者たちを保護するガバナンス構造もまた、ハードコーラルのレジームの維持に役立つ抑制型のフィードバックを生み出すことができる。
フィードバックを見えにくくする行動を防ぐ
ある種の活動や助成金は、抑制型のフィードバックを見えにくくしたり、歪んで見せたりすることがある。漁業の場合、ほとんどの業者は操業場所が法的に一定の海域に制限されている。つまり、乱獲は長期的に見た生計の選択肢を壊す恐れがあるので、彼らには乱獲しない動機があるということだ。しかし、海上を転々と移動するゲリラ漁船、つまり世界の海をあさり、その漁場を枯渇させる違法なもぐり漁船には、特定の漁場を持続可能な状態にしておく動機は何もない。だから彼らは海の秩序を乱す。言い換えるなら、彼らは世界を移動し続けることで、魚の資源量と漁獲量の間のフィードバックから逃れている。
緩やかに変化する重要な変数をモニタリングする
変数のモニタリングは緩やかな変化を発見する上で不可欠である。というのも、緩やかな変化は、システムが閾値を超え異なったレジームに再編成される原因になると考えられるためだ。しかし、財政的制約の煽りで、世界中のモニタリング・プログラムが削減されている。緩やかに変化する変数とフィードバックの役割を理解することは、管理者たちに次のことを気づかせるだろう。それは、システムの機能の根底にある変数に焦点を合わせたモニタリング・プログラムへの予算投入が、費用対効果を大いに高めるということである。
モニタリング情報に対応できるガバナンス構造を確立する
知識とモニタリング情報だけでは、生態系サービスを脅かす可能性があるレジーム・シフトを回避することはできない。モニタリング情報に効果的に対応できるガバナンス構造を確立することが同じくらい重要である。その革新的な事例の一つに、南アフリカのクルーガー国立公園で使われた方法がある。「潜在的な問題の閾値」と呼ばれるそのシステムが判断の基盤にするのは、主要な環境指標についての絶えず更新される知識である。監視した指標から、閾値が危険な状態に達したか、あるいは今にも達しそうなことが分かると、それを契機に公式な会議が開催され、その場で、救済措置を講ずるか、それとも危険の閾値を新しく設定し直すかについて、決定することが求められる。
主要メッセージ
急速に変化する世界で、緩やかに変化する変数とフィードバックを管理することは、社会・生態系システムが、重要な生態系サービスを生み出せるように"構成"し機能させていく上で、重大な意味を持つことが多い。こうしたシステムの構成やレジームがいったん変化すると、元に戻すことは極めて難しくなるだろう。
事例研究
貧困のわなを避けるタンザニア
フィードバックは、システムを望ましいレジームで維持するのに役立つ場合がある一方、望ましくない構成のままシステムを固定させてしまう場合がある。例えば、タンザニアの干ばつが多い地域では、人口増加によって穀物生産の需要が増え、休耕期間が短縮された。そのことが土中の有機物の枯渇と土壌肥沃度の低下を招いている。つまりそれは、穀物の生産量が少なく、農家には売るための余分な穀物がほとんどないか、皆目ないため、土壌肥沃度を回復、あるいは向上させるための化学肥料を買う資金がないことを意味している。その結果、彼らは貧困の悪循環に陥っている。このようなケースでは、システムを望ましくない構成で固定しているフィードバックを壊すか、弱める必要があると考えられる。例えばタンザニアでは、雨水採取と保全耕うんが土壌肥沃度の回復と干ばつの影響の緩和に役立つだろう。これによって、収穫の増加が期待できる。そうなると、小規模農家は財の蓄積を始め、それを使って化学肥料を購入することで、さらに収穫量を増やし、多くの農家がはまっている貧困の罠から抜け出せるようになるだろう。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-3/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則2 つながりの管理

Photo by Zane Persaud on Unsplash
つながりは、良いものにも悪いものにもなり得る。強固なつながりがあることによって、かく乱後の回復は促進される。しかし、強いつながりを持つシステムはかく乱をより速く拡大させる可能性もあるのだ。
つながりとは、ある社会・生態系システムのパッチ(同種の生物がまとまって生育する場所)生息地、群居する生物の生息圏を通って、資源や種、主体(アクター)が分散したり、移動したり、あるいは相互作用を行う構造と強さのことである。例えば、あるランドスケープの中でつながり合っている森林パッチについて考えてみよう。森林ランドスケープはシステムであり、森林パッチはそのシステムの一部である。森林パッチのつながり具合によって、生物が一つのパッチから別のパッチへどれくらい移動しやすくなるかが決まるのだ。どのシステムにおいても、つながりとは、さまざまな構成要素間の相互作用の性質と強さを意味する。社会的ネットワークという観点から見ると、人間はつながりという網目に組み込まれたシステム内の個々の主体(アクター)なのである。
つながりは、さまざまな方法で生態系サービスのレジリエンスに影響を与えることができる。つながりは、回復の促進とかく乱の拡大防止によって、生態系サービスをかく乱から守っている可能性がある。回復への影響は、サンゴ礁で実証されている。物理的な妨げがなく、サンゴ礁が隣接している生育地は、嵐などのかく乱で失われていたかもしれない種のコロニーを再形成する力を高めるのだ。その基本的な仕組みは、避難所としての役目を果たすエリアとのつながりが、かく乱を受けたエリアの修復を加速させ、その結果、サンゴ礁および関連する生態系サービスの維持に必要な機能が確実に保持されるというものだ。
おそらく、ランドスケープのつながりがもたらす最も良い影響は、生物多様性の維持に貢献できるということだろう。それは、しっかりとつながり合った生息パッチ間では、特定の場所である種が絶滅しても、周辺地域に生息する同じ種が流入してきて補うと考えられるためだ。道路やダムのような人為的な分断によりつながりが弱まると、個体群の生存率に悪影響が及ぶ。特に大型の哺乳類の個体群で、そうした影響が見られる。北米のイエローストーン・ユーコン間保全イニシアティブ[Yellowstone to Yukon Conservation Initiative:Y2Yのプロジェクトは、野生生物のコリドーを再構築することによって広い生息パッチ間を再びつなぐ保全計画の一例である。Y2Yの主要目的は、多様なステークホルダーのグループとのさまざまな共同イニシアティブを通して、130平方キロメートルに及ぶ、野生生物の中心的な生息地や主要なコリドーとして機能している8カ所の重要な地域をつなぐことである。
しかし、つながり過ぎが問題となる場合もある。つながりが限られていれば、山火事のようなかく乱の拡大に対する防壁の役割を果たし、生態系サービスのレジリエンスを高めることも時としてある。一方、過剰なつながりをもつシステムは、一斉に火事や病気といった同種のかく乱に見舞われ、個体群全体が影響を受けた場合には、個体群の生存率が低くなる可能性がある。
人間の社会的ネットワークでは、つながりは、ガバナンスの機会を向上・改善させることで、生態系サービスのレジリエンスを築くことができる。異なる社会集団間の固いつながりによって、情報共有は強化され、信用と相互関係を構築する助けとなる。ある主体(アクター)は、ほかの主体(アクター)との架け橋となり、その集団の課題に外部の視点と新しいアイデアをもたらすことも可能だ。しかし、ランドスケープに強いつながりが存在することによって、かく乱を一斉に被るリスクが高まるのとちょうど同じように、類似した知識を持ち、長期的なレジリエンスよりも目先の利益を選ぶ主体(アクター)が強くつながり合うと、悪い結果を招く恐れがある。研究によれば、行動基準が画一化すると、社会的主体(アクター)の探究能力が落ち、次のような状況が生まれるという。つまり、そのネットワークに属する全員の考え方が一様になり、実際は持続可能ではない方向へ進んでいるにもかかわらず、自分たちはうまくやっていると思い込んでしまうかもしれないという状況だ。
どうすればつながりをうまく管理できるのだろうか?
どの原則もそうだが、いざ実践するとなると、状況に左右されるのは避けられない。つながりを操作するということは一筋縄ではいかない取り組みなのだが、それでも、ガイドラインはいくつかある。
つながりを具体的に描き出す
つながりが生態系サービスのレジリエンスに及ぼす影響を理解するためには、まず、関連性のある部分とその大きさ、その相互作用とつながりの強さを特定する。それが終わったら、ビジュアル化とネットワーク分析のツールを利用すれば、ネットワークの構造を明らかにするのに役立つ。
重要な要素と相互作用を特定する
実行可能な介入方法を導き出し、つながりを最適化するためには、システムにある中心的なノード(交点)や孤立したパッチを特定することが重要である。そうすることで、システム内の脆弱な部分とレジリエンスのある部分を特定するのに役立つ。
つながりを修復する
つながりの修復にはノードの保全、創出、除去が必要だ。その一例が、カナダ、ケベック州南部のモンテレジー・コネクション(the Monteregie Connection)というプロジェクトだ。ここでは、森林と人がつながり合うことで、環境の変化に対するランドスケープとそのランドスケープの生態系サービスのレジリエンスが高まっている。
現在のつながりのパターンを最適化する
システムのレジリエンスを高めるには、システムのつながりを弱めたり、構造的に変えたりすること(例:モジュール化の促進)が有効だと思われるケースもある。例えば、2003年に米国とカナダ両国の東部一円で発生した停電では、5,000万人もの人が影響を受けたが、これは、密につながったシステムの局所的な障害が最終的にはシステム全体の破綻をもたらしたネットワークの一例である。
主要メッセージ
つながりは、社会・生態系システムとそうしたシステムが生み出す生態系サービスのレジリエンスを高めることも弱めることもできる。うまくつながったシステムは、より早くかく乱を克服し、回復できるが、システム内のつながりが過剰だと、システム全体にわたってかく乱が急速に拡大し、システムの構成要素すべてが影響を受ける可能性がある。
事例研究
カナダ、ケベックの多様な機能を持つランドスケープで供給される生態系サービス
ケベック州南西部に位置するモンテレジーは、大都市モントリオール近郊に位置し、農地や森林や村が点在する地域だ。この地域は、ハイキングや狩猟、メープルシロップの生産、農業など、数多くのレクリエーションや生活のための活動を支えている。この多様な機能を持つランドスケープ一帯で、研究者は明確な違いのある生態系サービスが6グループあることを見つけた。このグループはどれも、ランドスケープの特定のエリアに集まっており、一般的な社会・生態系サブシステムに分けられる。例えば、「村」グループは、森林レクリエーション・炭素隔離・土壌リン・土壌有機物・水質・鹿の狩猟で評価が高く、観光・自然観賞・養豚・作物で評価が低いという特徴があり、ランドスケープ上の「活動的な村のコミュニティを含む場所」に該当する。ほかのグループは、市町村レベルでは、「耕作地」、「作物と養豚の土地」、「観光」、「準郊外」、「別荘地」である。ランドスケープの全域にわたり、同じグループが繰り返し出てくることは、つながりなどのランドスケープの構成要素と、生態系サービスが提供するものとの間に関連があるという考え方を裏付ける。ランドスケープのつながりが生態系サービスの提供に直接与える影響に関しては、分かっていないことがまだ多くあるが、最近のモンテレジーの研究では、森林の分断が、近隣の農地における生態系サービスの提供に影響を与えることが示されている。例えば、生息地の分断をうまく管理すれば、生態系サービスの量とレジリエンスの向上に役立つ可能性もある。
該当ウェブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-2/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」原則1 多様性と冗長性の維持

Photo by Benjamin Davies on Unsplash
ある社会・生態系システムの中では、種やランドスケープの形式、知識体系、主体(アクター)、文化集団や組織といった構成要素はすべて、変化への対応や不確実性と驚きを取り扱う際に様々な選択肢を与える。
小規模農家は多くの場合、何種類もの食用作物を作付けする。どれかが不作でも食料の供給に壊滅的な影響がないようにするためだ。同様に、多種多様な種を対象とする天然資源の収穫システムは、単一種を対象とするシステムよりもレジリエンスが高い。いくつかの他分野の研究から、「多くの異なる構成要素から成るシステムは、構成要素の少ないシステムよりも一般的にレジリエンスが高い」ことを示す証拠が得られている。機能面の冗長性(同じ機能を果たせる構成要素が複数あること)があれば、一部の構成要素が失われたりうまくいかなくても、別の構成要素が補うことが可能になることで、システム内に「保険」をかけられることになる。要するに、冗長性とは「don't put all your eggs in one basket(卵を全部一つのかごに入れるな)」という英語の格言そのものなのだ。
冗長性は、それをつくり出すさまざまな構成要素が変化やかく乱に対して異なる反応を示す場合にはさらにいっそう有益となる。これがいわゆる「反応の多様性」である(ある特定の機能を果たす構成要素の大きさや規模が異なれば、その強みや弱みも違ってくるので、あるかく乱がすべての構成要素に対して同時に同じリスクを与える可能性は低くなる)。例えば、ウガンダの森林では、種子をあちこちに撒く役割は、ネズミからチンパンジーまで大きさの違うさまざまな哺乳類が果たしている。小型の哺乳類は局地的なかく乱の悪影響を受けるが、大型でより移動性の高い種であれば、そうしたかく乱の影響を受けないので、「種子をあちこちに撒く」という役割を果たし続けられる。
ガバナンス・システムにおいては、政府省庁やNGO、地域社会のグループといったさまざまな組織形態が機能面で重複することで、多様な反応を作り出すことができる。規模や文化、資金調達の仕組み、内部機構が異なる組織は、政治的・経済的な変化に対して、異なる反応を示す可能性があるためだ。社会・生態系システムのレジリエンスにおいては、それぞれに違った役割を担う、多様な主体(アクター)のグループが不可欠である。なぜならこういったグループは、それぞれに違った強みを持った上で重複した機能を果たすからだ。しっかりとつながり合ったコミュニティでは、機能が重複し、冗長性が見られ、活発な創造性と適応性を発揮することができる。
利用者と管理者が多様であることによっても、資源の持続可能な利用を守ることができる。例えば、漁村において、年齢や性別、財政手段の異なる人々は、好みの漁法や漁具も違うかもしれない。この多様性によって、コミュニティ全体での生態系の変化を発見し理解する能力が高まる。というのも、それぞれの利用者が見ているシステムの部分が異なるからだ。
多様性と冗長性への投資によって、人々の暮らしのレジリエンスを高めることができる。人々が市場や環境の変化に適応できるようになるからだ。例えば、南アフリカ共和国とナミビアの乾燥地帯では、文化的な生態系サービスに対する市場の選好が高まったことを受け、相当数の農家が牛の牧畜から野生動物のエコツーリズムに移行した。自分の農地の自然の生物多様性がそれほど損なわれていなければ、農家はこうした転換をより容易に行うことができる。
どうすれば多様性と冗長性を維持できるだろうか?
レジリエンスを構築するために、社会・生態系システムの管理における多様性と冗長性の価値を認識し、その価値を取り入れるマネジメントができるし、またそうすべきである。それは、以下のような点に注目すれば達成できる。
冗長性を維持し評価する
はっきりと分かる形で冗長性が保たれたり管理されることはほとんどないが、レジリエンスを作り出す上で冗長性は多様性と同じくらい重要である。特に焦点を当てるべきなのは、重要な機能やサービスだが冗長性が低いもの、例えば、主要な種や主体(アクター)によって制御されているものだ。場合によっては、こうした機能に関連する冗長性を高めることができるかもしれない。
生態系の多様性を維持する
受粉、有害生物制御、栄養循環、廃物浄化などの生態系サービスにとって生物多様性は不可欠だ。さらに、自然の生物多様性は、冗長性や反応の多様性の貯蔵庫を提供することによって、また農業システムにおいて、外部から投入する飼料や肥料、農薬への依存を減らすことによって、こうした生態系サービスのレジリエンスを高めることができる。生態系の多様性を維持強化するための戦略には、ランドスケープの複雑な構造を維持することや、影響を受けやすい地域の周辺にバッファー(緩衝地帯)を設置すること、つながるための「コリドー(回廊)【訳注:生物の生息地を結ぶ道となるエリア】」をつくること、そして過剰な数の種の侵入を制御すること等が含まれる。都市部では、豪雨による雨水の管理などで生態系サービスを提供する方法として、網目状に広がる緑地帯の「グリーンインフラ」を導入すれば、コンクリートパイプなどの「グレーインフラ」よりも、レジリエンスを高めることができる。
多様性と冗長性をガバナンス・システムに取り入れる
組織は知識の源が多様にあることの価値を認識し、うまく取り入れる必要がある。コストや、課題が対立するリスクとバランスをとりながらそれが行えるなら、多様な視点を持つことで、問題解決力を高め、学習とイノベーションの両方をサポートすることができる。こうして、かく乱からの回復をより早めることができるのだ。
コストがかかっても最大効率に重点をあまり置かない
従来の経済的思考は効率を最大化することを奨励するが、レジリエンス思考は生態系、市場、または対立に関わる衝撃によりうまく対処できるような政策を後押しする。代替となる開発プログラムの指針となるのは、相違と反応の多様性の原則である。例えば農村では、代わりとなる農業活動よりも、観光関連の活動などの農業とは異なる生計手段を選択できることが、反応の多様性を高め、ひいては衝撃に対するレジリエンスももたらすだろう。個人農家のレベルでそうした多様化を促すための具体的なインセンティブを設けることも可能だ。
事例研究
東アフリカ沿岸地域における生計の多様性と冗長性
東アフリカの沿岸部では、多様な生計手段(観光業、農業、臨時労働が含まれるだろう)の一つとして小規模漁業に従事する世帯が多い。生計を得るための活動を一つに特化することによって、世帯は総収入を最大にできるかもしれない。しかし、複数の選択肢から成る生計手段があれば、異なる生計手段が同じかく乱によって影響を受けない場合は特に、レジリエンスが高まる傾向がある(すなわち、生計の選択肢に関しては、多様な活動が反応の多様性と冗長性をもたらすのである)。例えば、多様な生計手段を持つ世帯であれば、治安に対する不安が国際的に高まり、観光部門が観光客の減少に痛手を負うときでも漁業活動を続けることが可能だ。いかなる生計源が影響を受けることになっても、多様な生計手段によりある程度のレジリエンスがもたらされる。また、漁業などの生計で取れ高の減少に直面しても、生計手段が多様であれば、柔軟性も高まる。ケニア、タンザニア、セイシェル、モーリシャス、マダガスカルの沿岸地域では、さまざまな生計手段を持つ世帯の漁師ほど、漁獲量が減少した時に、漁業から離れる可能性が高いことが分かっている。こうした生計の柔軟性は個々の世帯のレジリエンスを高めるだけでなく、漁場のような特定の生態系サービスを生み出すシステムの一部に対する圧力も緩和し、それによって、そのシステムのレジリエンスも高めることになるのだ。
主要メッセージ
多くの異なる構成要素(例:種、主体[アクター]、知識の源)をもつシステムは、構成要素の少ないシステムよりも一般的にレジリエンスが高い。冗長性があれば、一部の構成要素が失われたり、うまくいかなかったりしても、別の構成要素が補えることで、システム内に「保険」をかけることができる。冗長性を作り出す諸構成要素が、変化やかく乱に対して異なる反応を示す場合(反応の多様性)、冗長性はさらにいっそう価値をもつ。
該当ウエブサイト
https://applyingresilience.org/en/principle-1/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
「レジリエンス思考を適用する――社会・生態システムにおけるレジリエンス構築のための7つの原則」序文

Photo by David Marcu on Unsplash
この数十年間で、「レジリエンス」ほどよく知られるようになった概念はほとんどない。レジリエンスとは、システムの持つ、変化に対処し、発展し続ける能力である。ランドスケープや、沿岸地域、都市など、さまざまなシステムのレジリエンスが、どのように強化もしくは弱化されるのかに関する研究が急激に増えている。しかし、「レジリエンスを高める」とされる要因がたくさんあるため、「レジリエンスを築くのに不可欠なものは何か」と「そうした要因に関する知識をどのように適用できるか」についての理解が、分散し断片的になっているきらいがある。
レジリエンスの持続可能性へのアプローチが重視するのは、「想定外の変化に対処する能力をいかに構築するか」だ。このアプローチでは、人間を「生態系のダイナミクスを外側から動かすもの」として見ることから脱し、人間がいかに生物圏(地球を取り巻く大気や水、陸地を含む球状の領域で、あらゆる生命が見出される場所)の一部であり、生物圏と影響し合っているのかを見る。人間は主に、さまざまな生態系サービスを利用することを通して、生物圏に依存し、また相互に影響を与えている。例えば、調理や飲料として水を利用し、栄養源として作物を育てている。気候調整や、生態系との精神的・文化的なつながりなども生態系サービスの利用だ。人間はまた、農業や道路・都市の建設といった活動を通して、さまざまな点で生物圏を変化させている。人間が依存している欠くことのできない生態系サービスが、レジリエントに持続可能に供給され続けるためには、こうした人間と自然が相互に影響し合うシステム−−社会・生態系システム−−を、どのように管理するのが最善かを探ろうとするのがレジリエンス思考のアプローチだ。
この文書は、2014年にケンブリッジ大学出版局から出版された『仮邦題:レジリエンスの構築のための原則――社会・生態系システムにおける生態系サービスの維持』(Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services in Social-Ecological Systems)を一般向けに要約したものである。そして同書は、2012年に『Annual Reviews of Environment and Resources』誌に発表されたこれまでの研究を包括的にレビューした「仮邦題:生態系サービスのレジリエンスを高める原則に向けて』(Towards principles for enhancing the resilience of ecosystem services)をさらに詳しく解説したものである。社会・生態系システムとそのシステムが生み出す生態系サービスのレジリエンスを高めるものとして、さまざまな社会的・生態学的要因が提案されてきたが、この両文献は、そういった要因を概説し、評価したものである。そこでは、社会・生態系システムにおけるレジリエンスを構築するために不可欠だと考えられる「七つの原則」を提示し、これらの原則を実際に適用するにはどうしたらよいかが論じられている。七つの原則とは、1)多様性と冗長性の維持、2)つながりの管理、3)動きの遅い変数とフィードバックの管理、4)複雑で適応型のシステム思考の育成、5)学習の奨励、6)参加の拡大、7)多元的なガバナンス・システムの促進、である。
次章以降では、各原則を説明し、どのように適用されたかの例を挙げている。言うまでもなく、レジリエンスを構築するための万能薬はない。それどころか、ここで示す原則はすべて、「いつ、どこで、どのように適用すべきか」「原則同士がどのように相互に影響し合い、依存し合っているのか」について、微妙な違いも含めての理解を要する。どの原則を適用するにしても、まずは「何の」「何に対する」(火災、洪水、都市化など)レジリエンスを構築したいのかを考えることが必須である。あるランドスケープにおける既存の生態系サービスのレジリエンスをただ高めるだけでは、不平等を定着させ悪化させてしまう恐れがある。例えば、上流の私有地での農業活動や林業活動が引き起こした洪水の影響に、都市部の貧しいコミュニティが苦しむ、といった具合だ。異なる生態系サービス(作物の生産と生物多様性など)の間には重大なトレードオフが存在しており、すべての生態系サービスのレジリエンスを同時に高めることはできない。こうした注意点を念頭に、七つの原則は、社会・生態系システムに介入し、"力を合わせる"上で鍵を握る機会についての指針を示している。それは、急速に変化し、ますます過密化する世界にあって、社会・生態系システムのレジリエンスを決して失うことなく、人々の幸福を維持し支えるために必要な生態系サービスを提供できるようにするためのものなのである。
該当ウエブサイト
https://applyingresilience.org/en/the-7-principles/
本書は、2015 年にストックホルム・レジリエンス・センター(Stockholm Resilience Centre)により、"Applying resilience thinking - Seven principles for building resilience in social-ecological systems" の表題で発行された文献です。
この日本語訳版に関する責任は、すべて幸せ経済社会研究所にあります。
レジリエンスを高める自然災害伝承碑の活用
日本は昔から、台風・津波や洪水、火山の噴火など、数多くの自然災害に見舞われてきました。災害の被害を減らすために、堤防や盛土の整備、ハザードマップの作成など、さまざまな取り組みが行われています。こうした取り組みの中で、近年注目を集めているのが、「自然災害伝承碑」の活用です。
自然災害伝承碑とは、 過去の津波、洪水、火山といった自然災害の被害状況などが記載されている石碑や像などのモニュメントのことです。古いものでは、千葉県の一宮町に1694年(元禄7年)に建立された「延宝の津波供養塔」があります。
自然災害伝承碑は、減災や防災にどういう形で役立つのでしょうか。例えば、広島県坂町では、2018年7月の西日本豪雨災害で死者行方不明者18名、全半壊家屋が1250棟を超える甚大な被害を受けました。実はこの土地には、1907年(明治40年)に起きた大水害の被災状況を伝える石碑があるのですが、 地域に暮らす人々にその伝承内容が十分に伝えられていませんでした。もし、過去に水害があったことを知っていれば、もっと早く避難できたかもしれません。
このような事例が各地にあることから、国土地理院では「災害への備え」を支援する取り組みとして、2019年度から自然災害伝承碑の情報を地図に掲載する試みをはじめています。
レジリエンスを高める災害対策
せっかく自然災害伝承碑があっても、その存在が地元住民に忘れられてしまう理由としては、建立してから長い時間が経っていることや、昔に比べると人口の移動が激しいといった理由が考えられます。あるいは堤防や盛土といった対策が進んだことによって、「もう災害は起こらないだろう」と安心してしまうことも一因でしょう。しかし、堤防が決壊してしまう事例や、盛土があるという安心感から避難せずに被害にあってしまったという事例も多数あります。堤防や盛土によって、通常の大雨の被害を防ぐことが出来たとしても、「100年に一度」といった規模の大きな災害を防げるとは限らないのです。
だからこそ、堤防や盛土といった技術を用いたハードな防災・減災対策とともに、ハザードマップの作成や自然災害伝承碑の活用、防災訓練などソフトな防災・減災対策を行うことが必要です。このように一つの手段に頼らず、複数の手段を備えておくことは、「冗長性を高める(※)」という意味でレジリエンスを高めることにつながります。
国土地理院のサイトには2020年11月現在約650の自然災害伝承碑のデータが掲載されています。お住まいの地域のそばに自然災害伝承碑がないか調べてみてはいかがでしょうか?
※冗長性とは
冗長性とは、同じ機能を果たす構成要素が複数あることを指します。英語の格言に、「don't put all your eggs in one basket(卵を全部一つのかごに入れるな)」というものがあります。同じかごにすべての卵を入れてしまうと、そのかごを落としてしまったら、卵はすべて割れてしまいます。防災でも、一つの手段に頼らずに複数の対策を行うことで、「保険」をかけることができます。
参考資料
国土交通省国土地理院「自然災害伝承碑」(ウェブサイト)
農業の底力=「食料自給力」 にも注目!
「日本の食料自給率が約40%」という話は聞いたことがあるでしょう。食料自給率とは、「国内の食料消費が、国産でどの程度賄えているか」を示す指標です。
これに対して、日本の「食料自給力」とは、、国内の農地等をフル活用した場合、国内生産のみでどれだけの食料を生産することが可能か(食料の潜在生産能力)を試算した指標です。その構成要素は、農地・農業用水等の農業資源、農業者(担い手)、農業技術 と整理されています。
食料安全保障に関する国民的な議論を深めていくために、平成27年3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」において、初めて指標化されました。
平成25年度の食料自給力指標を見ると、現実の食生活とは大きく異なるいも類中心型(パターンC・D)では、推定エネルギー必要量等に達するものの、より現実に近い米・小麦・大豆中心型(パターンA・B)では、これらを大幅に下回る結果となっています。
食料自給力指標は、日本の農林水産業が持つ「底力」を見るための指標です。計算上、作付転換に要する期間を考慮しない等の大胆な前提を置いているため、「いざという時にどれだけの食料を生産できるか」という能力を見る指標ではないと断りがありますが、食料自給力は近年低下傾向にあり、将来の食料供給能力の低下が危惧される状況にあるとされています。
将来の食糧供給能力を支える底力にも注目し、高める取り組みを進めていくことは、日本のレジリエンスを高めることにつながります。
(出典:http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html)